 Nスタイルホームは創業14周年を迎えました。
Nスタイルホームは創業14周年を迎えました。
 Nスタイルホームは創業14周年を迎えました。
Nスタイルホームは創業14周年を迎えました。
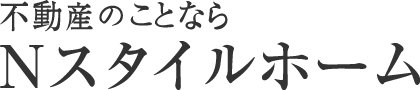
死後に認知された相続人による遺産の支払請求で、新しい判例が出たと聞きました。どのようなものですか?
これまで相続債務の控除をめぐって下級審判決が分かれ、学説は控除説が有力でしたが、この度、最高裁で非控除説の判断が出ました。以下で説明します。
平成20年2月3日、Aが死亡しました。XはBとA間の子でAの死後、認知を求める訴え(死後3年可)を東京家庭裁判所に提起し、平成24年12月14日に認知判決が確定しました。確定前の亡Aの相続人は嫡出子Yと妻Cであり両名は平成20年3月31日協議で遺産を分割済みです。
Xは平成27年、YCに対し、民法910条による価額支払請求を東京地方裁判所に提起しました。審議中にCが死亡しYおよび(Yの妻でCの養子)DがCを相続。XはCに対する訴えを取下げ、Yに対し遺産の評価額合計(9941万余円)に特別受益2500万円を加えた金額の4分の1(3110万余円)を請求し、Yの医系大学・大学院の学費、入学寄付金、医院併用住宅の無償使用等を特別受益と主張しました。
Yは特別受益を否認し、支払額は遺産の価額から相続債務(葬儀関連費用255万余円および亡Aの20年度特別区・都民税37万余円)を控除した残額の6分の1であると答弁。東京地裁は特別受益は認めず、平成25年最高裁大法廷決定を引用し(注)、非嫡出子Xの法定相続分を4分の1と判示し、「相続開始後の認知で相続人となった者が遺産分割を請求する場合、対象は遺産分割の対象となる積極財産に限られる」「可分債務の債務者が死亡し相続人が数名あるときは債務は当然分割され各相続人に相続分に応じて承継される」と債務の控除を否定し、積極財産の4分の1(2485万余円)の支払いを認容しました(東京地裁 平成29年9月28日判決)。
双方控訴。Yは「Cが払ったAの特別区・都民税と葬儀関係費用の各4分の1につきCのXに対する不当利得返還請求権を相続したからこれを自働債権としXの本件請求債権を受働債権として対当額で相殺する」と相殺の抗弁。
東京高裁は、「Cの相続人はYD両名であるからYの相続した納税に係る不当利得返還請求権は4万円余に留まる」として相殺を認め(遅延損害金14日分の一部に充当)「葬儀費用は元来相続債務ではない。相続人が負担するべき債務であるとしてもXは葬儀に参列する機会すら与えられていないから返還債務を負うとは言えない」とこの相殺は認めず、積極財産の4分の1(2485万余円)と前記納税の不当利得返還請求権の相殺残額(1073円)を認容しました(東京高裁 平成30年5月24日判決)。
Y上告で最高裁は「910条は死後認知の相続人とすでに分割を終えた共同相続人との利害の調整を図るものであるから分割の対象とされた遺産の価額を基礎として算定するのが衝平の観点から相当である。相続債務は認知された者を含む各共同相続人に当然承継され、遺産の分割の対象とならない」と非控除説を明示して上告を棄却。
実務でも相続債務は遺産分割の対象外とするのが一般的です(最高3小 令和元年8月27日判決 判例秘書L07410065)。
(注)非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条4号但し書の部分を憲法14条1項違反とした平成25年9月4日最高大法廷決定
Nスタイルホームへのお問い合わせは…